


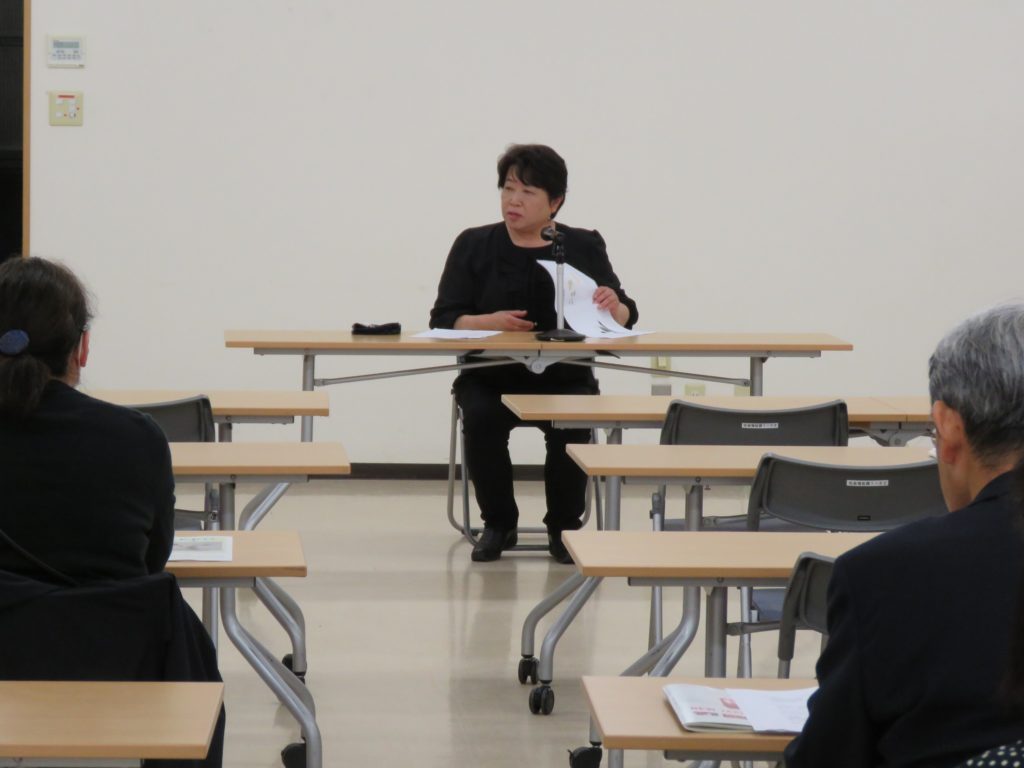
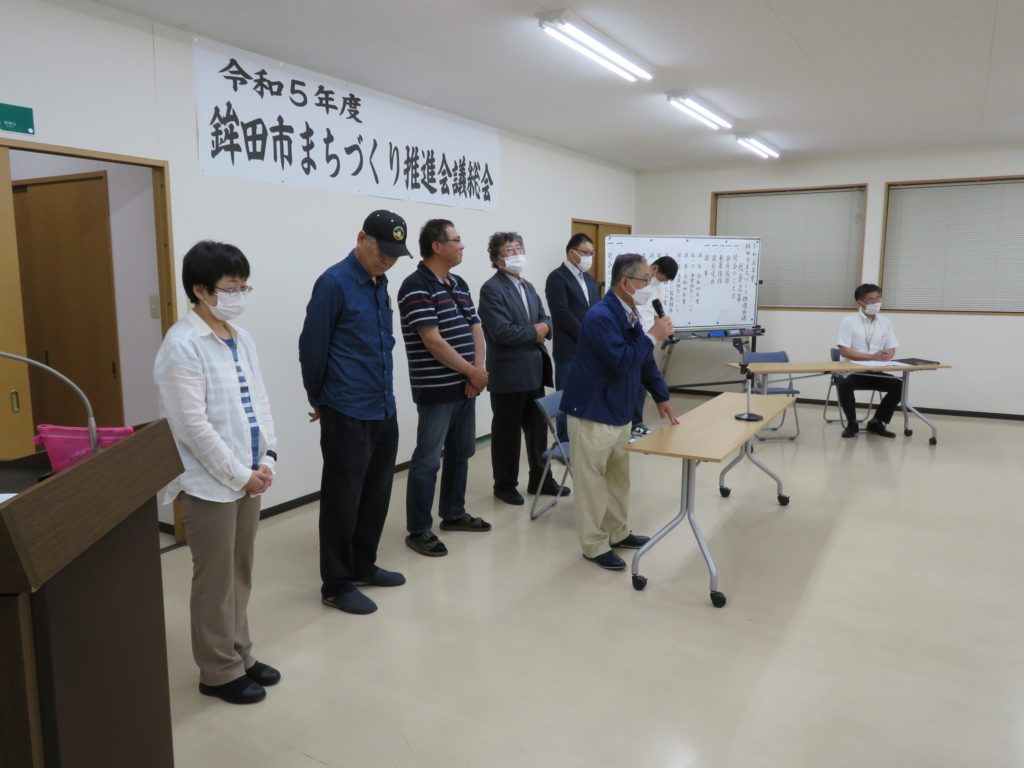



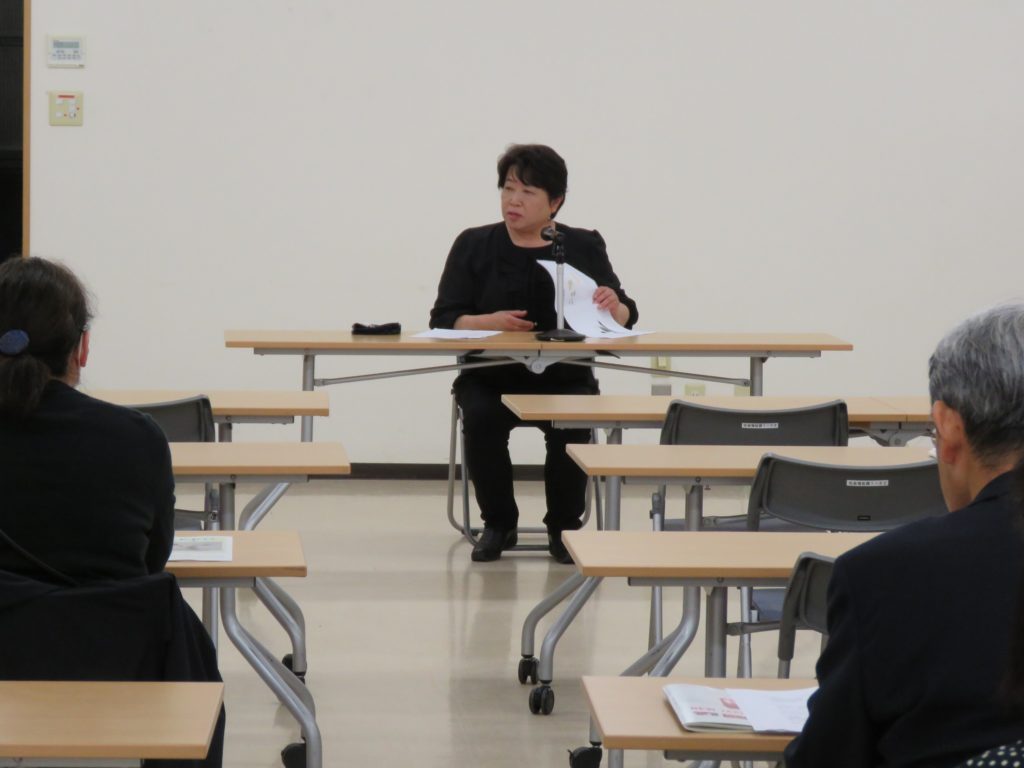
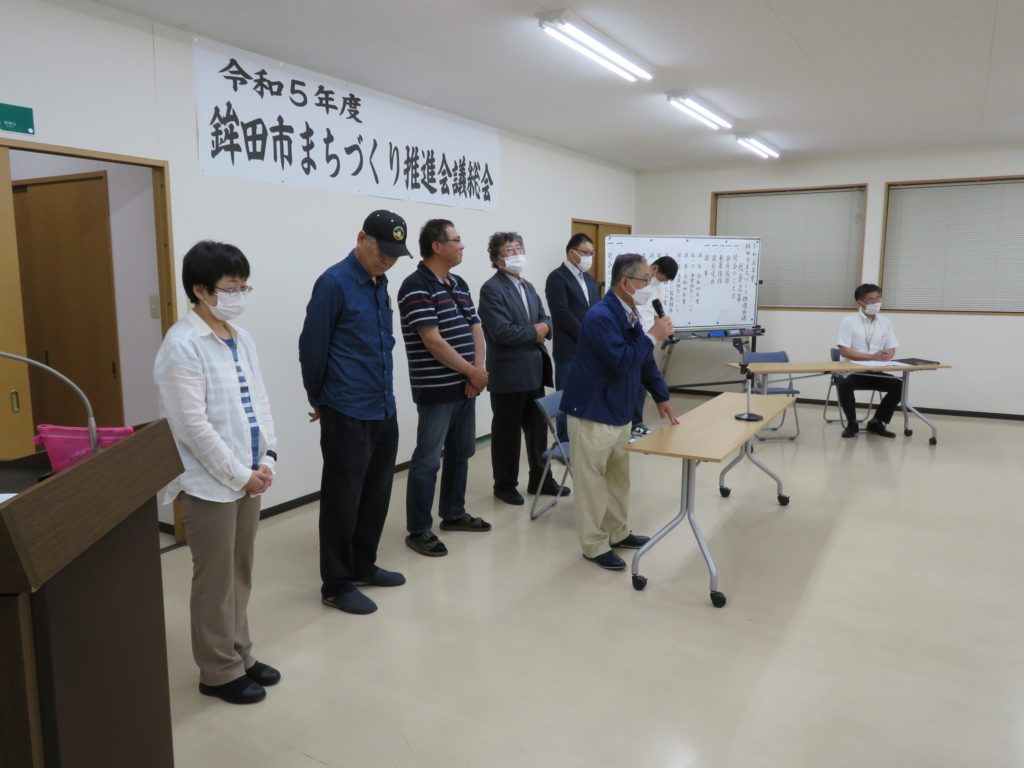
2018年12月1日(土)9:00~11:30 天気:快晴
仲間づくり部会により「ほこたカルタを歩こう会 ー 無量寿寺とほこた道・とりのす道を歩く ー」を開催しました。鳥栖の無量寿寺を起点に、ほこた道・とりのす道の計 7 kmを歩きました。16名の参加がありました。
<ほこた道・とりのす道って?>
主に江戸時代に相馬藩、仙台藩によって使われていた物資輸送ルートです。米等を船で江戸に運ぶ途中、涸沼から巴川(北浦)まで馬で運ぶ陸送ルートがありました。昔は駄賃を稼ぐ人夫が大勢いたのでしょうね。
■ほこた道(相馬藩の物資輸送ルート)
涸沼(宮ヶ崎河岸)→ 舟木 → 冨田 → 巴川(鳥栖河岸)
■とりのす道(仙台藩の物資輸送ルート)
涸沼(網掛の仙台河岸)→ 宮ヶ崎原 → 舟木 → 冨田 → 鳥栖 → 巴川(塔ヶ崎河岸)
(なお、この他にも、涸沼(海老沢)と巴川(大和田)を結ぶ水戸藩の物資運搬ルートがあります。ここはまたの機会に。)
「ほこた道」と「とりのす道」は、冨田地内で近接します。今日は、鳥栖河岸跡から「ほこた道」を北上し、冨田地内の近接地点から「とりのす道」に移り南下、鳥栖新田から無量寿寺に戻るコースをたどりました。
<道中のもよう>

教法塚・・・1593年親鸞聖人の足跡を巡る旅の途中、鳥栖無量寿寺で客死した「教法」が、無量寿寺住職と新堀氏によってこの場所に葬られています。教法は一向一揆石山合戦(1570-1580)で織田信長軍と戦いましたが、新堀氏も無量寿寺から石山合戦に赴いており、教法とは戦友の関係にありました。
以上、行事のもようをお伝えしました。このような企画をこれからも行っていきますので、是非多くの方々に参加していただきたいと思います。いっしょに鉾田の歴史を再発見しましょう。
ほこたカルタに登場する名勝・史跡を訪ねて歩く企画です。今回は、ほこたカルタには出てきませんが旧大洋地区の史跡を歩いて巡りました。
快晴の天候に恵まれ、24名の参加者がありました。最年少は小学2年生でした。7 km 強のウォーキングに出発です。
鉾田市社会福祉協議会大洋支所前を出発し、北北東に進み、たきもとクリニック前を通過し、上島東小学校脇の第1目的地「汲上如意輪観世音」に到着しました。
この観音様は、安産厄除として信仰が厚いそうです。観音菩薩を信仰した仙台藩とのつながりもあったとか。かつて2月の縁日には露店や見世物でたいそうな賑わいをみせたそうで、とりわけ夜は若い男女の出会いの場として有名だったとのことです。
次に、南に進路をとり、水戸と銚子の飯沼観音を結ぶ第二目的「飯沼街道」を、地元のお年寄りとすれ違ったりしながら、歩いていきました。
上沢地区で右折し、西にさらに進み、元の場所近くに戻ってきました。最後の第三目的地は、台地の下に降りていった所にある「福泉寺」です。
福泉寺には国指定重要文化財(彫刻)の「釈迦如来立像(しゃかにょらいりゅうぞう)」があります。鎌倉時代末期に制作されたというこの如来像を特別に見せていただきました。長い歴史を感じさせる美しい木製の如来像であり、背景の彫刻も見事で年月を経た金箔が味わい深いものとなっていました。なお、本堂の天井に描かれた竜の絵も素晴らしいものでした。
釈迦如来立像の前で記念撮影です。
こうして無事スタート地点に戻ってきました。おしゃべりをしながら適度に体を動かして、地域の歴史・文化に触れ、楽しい有意義な時間を過ごすことができました。